涅槃会とは?お釈迦様の入滅を偲ぶ仏教行事とは?涅槃会とは?由来や意味、儀式や現代での意義を解説
2月15日の涅槃会は、お釈迦様の入滅を偲び、悟りの境地を称える仏教行事。三大法会のひとつで、遺徳を偲び、涅槃図を拝観します。輪廻からの解脱、つまり悟りへの道を示す教えに触れ、感謝を捧げる日。涅槃団子や花供御を供え、甘酒が振る舞われます。無病息災を願い、お釈迦様の教えを心に刻みましょう。
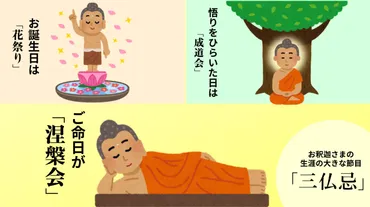
💡 涅槃会は、お釈迦様の入滅を偲ぶ仏教の重要な行事であり、毎年2月15日頃に行われるのが一般的です。
💡 涅槃会は、お釈迦様の教えを振り返り、悟りの境地である涅槃について理解を深める機会となります。
💡 涅槃会では、涅槃図の公開、読経、法話、そして様々な供え物やお布施が行われます。
本日は涅槃会について掘り下げていきます。
仏教行事としての意味合い、歴史、そして現代におけるその重要性について、詳しく見ていきましょう。
涅槃会:お釈迦様の悟りを称える日
涅槃会は何を記念する日?
お釈迦様の入滅日
涅槃会について深く知るために、まずその基本的な情報から見ていきましょう。
公開日:2025/03/05
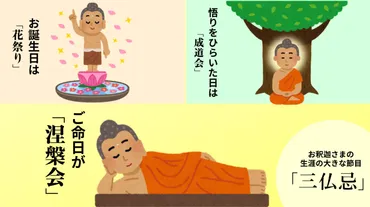
✅ 2月15日は仏教の「三仏忌」のひとつである「涅槃会」であり、お釈迦さまが亡くなられた日を偲ぶ重要な行事です。
✅ お釈迦さまの命日は明確には伝わっておらず、南方仏教では5月、中国や日本では2月に涅槃会が行われるようになりました。
✅ 「涅槃会」では、お釈迦さまが亡くなった際の涅槃図を掲げ、法要が行われます。涅槃図はお釈迦さまの入滅の姿を描写し、日本の「北枕」の風習などもその影響を受けていると考えられています。
さらに読む ⇒宮城県仙台市浄土宗十念寺出典/画像元: https://zyunenzi.jp/blog/680/涅槃会は、お釈迦様の入滅を悼むだけでなく、その教えを現代に活かすための大切な機会ですね。
私も、お釈迦様の入滅の姿を描いた涅槃図を見て、その教えを心に刻みたいと思いました。
涅槃会は、仏教の開祖であるお釈迦様の命日にあたる日に仏教寺院などで行われる特別な法要です。
仏教の三大行事(三仏会)の1つとされ、熱心な仏教徒にとって重要な1日となっています。
毎年2月15日に行われ、お釈迦様の入滅を「大般涅槃」と呼び、生前のお姿を偲び、思いを馳せる習慣が根付いています。
涅槃には「解脱」という意味があり、人間が生死の中で繰り返す輪廻転生からの解脱を表しています。
言い換えると、涅槃とは一切の煩悩を打ち消した「悟りの世界」を表す言葉でもあります。
悟りの世界は生死をも超越した存在で、仏教において最終最後の目的地となっています。
つまり、涅槃会はお釈迦様の入滅を悲しむ法要ではなく、生前1人で悟りの境地に辿り着いた偉業を称える日でもあります。
へえ、涅槃会って、そういう意味があったんですね!お釈迦様の最期って、なんかドラマチックで興味深いですね!
涅槃会の由来と意義
涅槃会は何を記念する行事?
お釈迦様の入滅
次に、涅槃会の由来や意義について、さらに詳しく見ていきましょう。

✅ 記事は、涅槃図に描かれた阿難尊者、阿泥樓駄尊者、迦葉童子の3人の人物像とその特徴について解説しています。
✅ 阿難尊者は、お釈迦様の十大弟子の一人であり、お釈迦様の侍者として25年間仕え、多くの教えを記憶していたことから「多聞第一」と呼ばれています。
✅ 阿泥樓駄尊者は、お釈迦様の十大弟子の一人で、阿難尊者を励ます場面が描かれており、迦葉童子は、涅槃経の会座で悟りを開いた12歳の童子であり、涅槃経を受持する大役を担っている人物です。
さらに読む ⇒浄土宗 心行寺出典/画像元: https://www.shingyouji-yokohama.or.jp/posts/5625509/なるほど、涅槃会は、お釈迦様の遺言を私たちが理解し、実践するための重要な機会なのですね。
お供え物にも深い意味が込められていることに感銘を受けました。
涅槃会は、お釈迦様の入滅の日(命日)に行われる法要で、旧暦2月15日に行われます。
お釈迦様の遺徳を偲びつつ、遺教経を読経し、『涅槃図』というお釈迦様の最期を描いた絵画を掲げます。
涅槃会は、お釈迦様の入滅を悼むだけでなく、悟りの境地である涅槃について理解を深める機会でもあります。
涅槃会の由来は、お釈迦様が80歳で入滅された際に、弟子である阿難尊者に「この世のものはすべて変化し続ける。
怠らず精進しなさい」と遺言を残したことから来ています。
お釈迦様の入滅は、肉体の制約から解放され完全な涅槃へと至ったことを意味し、『無余涅槃』と呼ばれます。
涅槃会では、お供え物として団子や『花供僧』と呼ばれる小さなおかきが用いられます。
これらの供え物は、お釈迦様の御下がりとして、参加者に振舞われ、無病息災を願う意味が込められています。
涅槃会の由来、勉強になります!阿難尊者とか、登場人物も興味深いですね。お供え物にも意味があるなんて、奥が深いですね。
次のページを読む ⇒
お釈迦様の入滅を偲ぶ涅槃会。2月15日、涅槃図公開や法話、甘酒などで、仏教の教えに触れる。感謝と学びを深める、大切な仏教行事。

