生レバーは危険?食中毒リスクの現状と対策を徹底解説生レバーの食中毒リスクとは!?
生レバー食中毒、実は牛肉の50倍以上!😱 腸管出血性大腸菌などのリスクから、2012年から販売・提供禁止に。安全な生食方法はないので、加熱して美味しく食べよう!
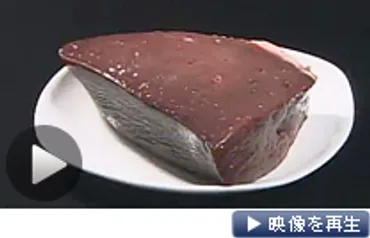
💡 生レバーは食中毒のリスクが高い食材である
💡 生レバーの販売・提供は法律で禁止されている
💡 食中毒予防には、食品衛生の3原則を守ることが重要である
では、まず生レバーの食中毒リスクについて詳しく見ていきましょう。
牛レバーの食中毒リスクの現状
生食用牛レバーの食中毒リスクは?
非常に高い
生レバーの食中毒リスクは、近年、改めて注目されていますね。
公開日:2011/12/15
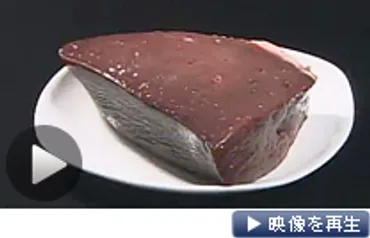
✅ 厚生労働省の調査で、食肉処理された牛のレバー内部から腸管出血性大腸菌O157が検出された。これは、レバー内部から腸管出血性大腸菌が確認された初の事例である。
✅ 調査では、牛の胆汁でO157が増殖することが判明し、腸管にいるO157が胆のうに移動し、レバー内部に入り込む可能性が示唆された。
✅ 厚生労働省は、生レバー提供禁止を検討し、飲食店などで生レバーを提供する際の規制強化の可能性がある。
さらに読む ⇒日本経済新聞 - ニュース・速報 最新情報出典/画像元: https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG15017_V11C11A2CR0000/生レバー内部から腸管出血性大腸菌が検出されたという事実は驚きです。
消費者としては、このような情報を知り、安全な食生活を送るために注意する必要があります。
生食用牛レバーによる食中毒の発生件数は、平成10年から22年までに116件と、同時期の生食用牛肉を原因とする食中毒の5件と比較して非常に多いことが明らかになっています。
食品中の食中毒汚染実態調査結果によると、平成11年から22年度における生食用牛レバーの腸管出血性大腸菌O157及びカンピロバクターの汚染率はそれぞれ0.7%、4.6%でした。
さらに、厚生労働科学研究では、牛レバーのカンピロバクター汚染率は11.4%と報告されています。
これらの調査結果から、生食用牛レバーは食中毒のリスクが高いことが示唆されており、その安全性確保に向けた対策が急務となっています。
え、生レバーってそんなに危険なんですか?今まで何も気にせず食べてたんですけど...
生食用牛レバーの販売・提供禁止
牛のレバーの生食はなぜ禁止されたの?
食中毒のリスクがあるから
生レバーと生卵の違いについて詳しく解説していただきありがとうございます。

✅ 生レバーと生卵における食中毒リスクの差は、腸管出血性大腸菌とサルモネラ菌の発症菌数と胃酸への抵抗性の違いによる。
✅ 腸管出血性大腸菌はサルモネラ菌よりも発症菌数が少なく、胃酸への抵抗性が高い。そのため、生レバーには少量の腸管出血性大腸菌でも食中毒のリスクが高い。
✅ 一方、サルモネラ菌は発症菌数が多く、胃酸への抵抗性が低い。そのため、生卵には大量のサルモネラ菌が含まれていても、胃酸で死滅するため、食中毒のリスクは低いと考えられている。
さらに読む ⇒食品微生物学(検査と制御方法)|基礎と最新情報を解説|木村 凡出典/画像元: https://foodmicrob.com/acid-reistance-salmonella-vs-escherichia-coli/生レバーと生卵の食中毒リスクの違い、よくわかりました。
生レバーは、サルモネラ菌よりも発症菌数が少ない腸管出血性大腸菌によって食中毒のリスクが高いんですね。
2012年7月1日より、食品衛生法に基づき、牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供が禁止されました。
これは、牛の肝臓から重篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあり、安全な生食方法がないためです。
厚生労働省は、リーフレットを制作し、全国の自治体を通じてこの禁止措置を行う理由を周知するとともに、消費者に対しても生食用としての販売・提供が禁止されたことを周知徹底し、生食をしないことへの理解を求めています。
生レバーの販売が禁止になったのは、知らなかったです。今まで、お店で生レバーを見かけたら、安心して食べちゃってたんですけど…
食中毒発生リスクと対策
豚の生レバーも危険ってホント?
食中毒リスクあり
カンピロバクター食中毒のリスクが高いんですね。

✅ カンピロバクター食中毒は、生レバーなどの生肉を食べることで発生する可能性が高い。特に、鶏肉はカンピロバクター菌を保有している割合が高いため、十分な加熱が必要である。
✅ カンピロバクター食中毒のリスクを下げるには、リスクの高い店に行かないことと、リスクの高い食材を回避することが重要である。リスクの高い店とは、衛生管理が徹底されていない可能性のある店であり、リスクの高い食材とは、生肉や十分に調理されていない肉である。
✅ 今回の食中毒事件は、チェーン店で発生した。チェーン店では、本部の目が行き届かない部分があり、食中毒予防の意識が十分に浸透していない可能性がある。そのため、個人店で、信頼のおける料理人が作る料理を食べる方が安全である。
さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/09a805946b9ce952cf9ac65969028dc1e290d2eeチェーン店で食中毒が発生したというのは、とても怖いですね。
安全なお店選びも、食中毒予防には大切だと改めて感じました。
牛レバーだけでなく、豚の生レバーもE型肝炎や食中毒のリスクがあり、生食は避けるべきです。
食肉を生で食べることは、新鮮かどうかに関わらず、食中毒のリスクがあります。
事業者向けには、牛レバーは加熱用として販売・提供しなければならず、レバ刺しの提供は禁止されています。
また、牛レバーを使用する際には、中心部まで十分に加熱する必要がある旨の情報を提供する必要があります。
牛レバーだけでなく、豚の生レバーも危険なんですね。生肉は、やっぱり十分に加熱して食べるのが安全ですね。
食中毒予防のための3原則
食中毒を防ぐにはどんなことに気をつければいい?
3原則を守りましょう
食中毒は、細菌、ウィルス、寄生虫、化学物質など、様々な原因で起こるんですね。

✅ 食中毒は細菌、ウィルス、寄生虫、化学物質などが原因で起こる健康被害であり、腹痛、下痢、嘔吐などの症状を引き起こします。近年は衛生管理の徹底により減少傾向にあるものの、依然として発生しており、特に夏場は気温と湿度の影響で細菌性食中毒のリスクが高まります。
✅ 食中毒は細菌性、ウィルス性、化学性、自然毒、寄生虫の5つのタイプに分けられ、それぞれのタイプで原因となる物質や症状が異なります。細菌性食中毒は、感染型、食物内毒素型、生体内毒素型に分類され、代表的な細菌としては腸炎ビブリオ、カンピロバクター、サルモネラ菌などがあります。
✅ 食中毒を防ぐためには、食品の衛生管理が重要です。特に、生肉や魚介類は十分に加熱し、調理器具や食器も清潔に保つ必要があります。また、手洗いやうがいを徹底し、食品の保管にも注意が必要です。特に夏場は、室温での放置時間を短くし、冷蔵庫で適切な温度に保つことが重要です。
さらに読む ⇒医療・介護用品の通販サイト|HeartPlus【ハートプラス】出典/画像元: https://www.heart-p.jp/blog/food-poisoning/食中毒を防ぐには、食品の衛生管理が重要なんですね。
特に夏場は、細菌性食中毒のリスクが高まるので、注意が必要です。
食中毒の予防には、食中毒の原因となる細菌等を『付けない、増やさない、やっつける』の3原則を守ることが重要です。
特に夏場は、食中毒の発生が増加する傾向があるため、食中毒の予防に努めるよう呼びかけています。
牛レバーの生食は、食中毒のリスクが非常に高いため、安全のためにも生食は避け、中心部まで十分に加熱して食べるようにしましょう。
食中毒予防の3原則、とても分かりやすいです。生レバーは、生食は避け、十分に加熱して食べるようにします。
今回の記事では、生レバーの食中毒リスクについて詳しくご紹介しました。
生レバーは、食中毒のリスクが高い食材であることを改めて認識し、安全な食生活を送るように心がけましょう。
💡 生レバーは食中毒のリスクが高いため、生食は禁止されている
💡 生レバーを食べる際は、中心部まで十分に加熱する必要がある
💡 食中毒予防には、食品衛生の3原則を守ることが重要である


